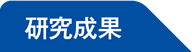重要管路の再構築に関する研究
基幹管路を対象に、更新に合わせて冗長性を持たせる、
更新・再構築の計画手法を研究しました。
 再構築モデルにおける計画策定手法の検討
再構築モデルにおける計画策定手法の検討更新が難しいとされている、大口径・単線の基幹管路を対象に、更新に合わせて、緊急時や次期・次々期の更新工事に備えて冗長性を持たせ、更に需要減少にも対応できる計画策定手法を検討しました。冗長性を持たせる整備手法として、「二重化」、「ループ化」、「系統連絡」を取り上げました。
仮想のモデル管路である再構築モデルにおける、計画策定のシミュレーション並びに計画実施事例の調査を行うことにより、更新・再構築計画策定フロー(素案)を作成しました。
| 整備手法 | 定義 |
|---|---|
| 二重化 | 既設管と同じ路線で、新設管整備+既設管にPIPを行う |
| ループ化 | 任意節点から隣接した節点に、最短で連絡する路線の整備を行う |
| 系統連絡 | 浄水場間、配水池間を連絡する管路の整備を行う |
 実管路モデルにおける計画策定手法の検証
実管路モデルにおける計画策定手法の検証実管路をモデル化した実管路モデルにおいて、計画策定のシミュレーションを行い、更新・再構築計画策定手順の検証を行いました。その結果を踏まえて、計画策定フロー(素案)を一部修正し、更新・再構築計画策定フローを作成しました。
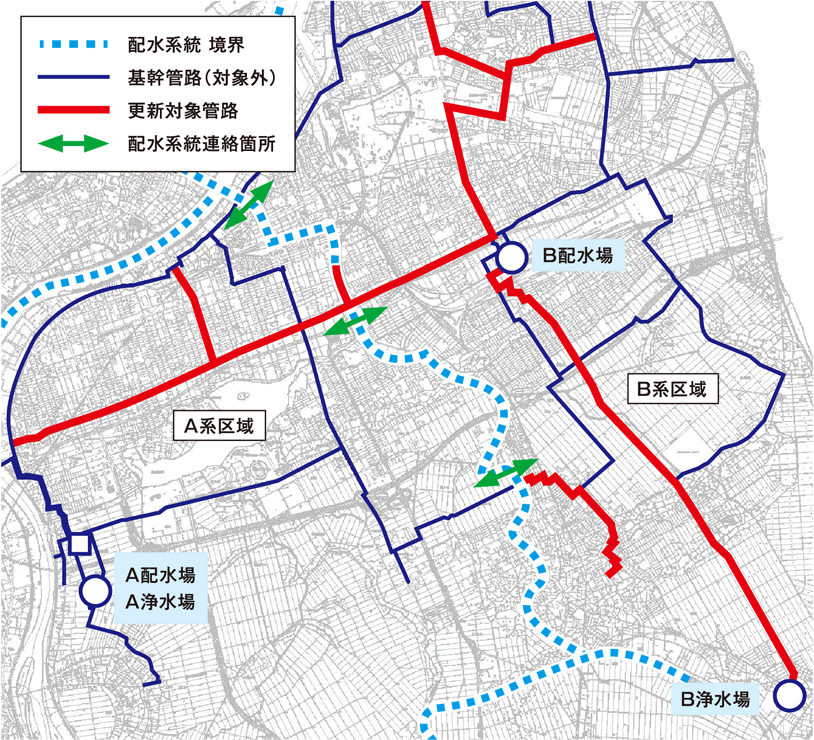
 基幹管路の更新・再構築計画策定手順
基幹管路の更新・再構築計画策定手順次の3つを手順とする計画策定フローを新たに作成しました。
 基幹管路システムの設定
基幹管路システムの設定基本情報の整理を行い、基本方針の設定と想定事象の抽出を行う。
 基幹管路システムの現況評価
基幹管路システムの現況評価管路の物理的評価、重要度評価に、新たに冗長性評価を加えてまとめる。
 基幹管路システムの再構築計画
基幹管路システムの再構築計画冗長性を有する「二重化」、「ループ化」、「系統連絡」及び冗長性がない「単純更新」を、便益や費用の面から比較して整備案を選定する。
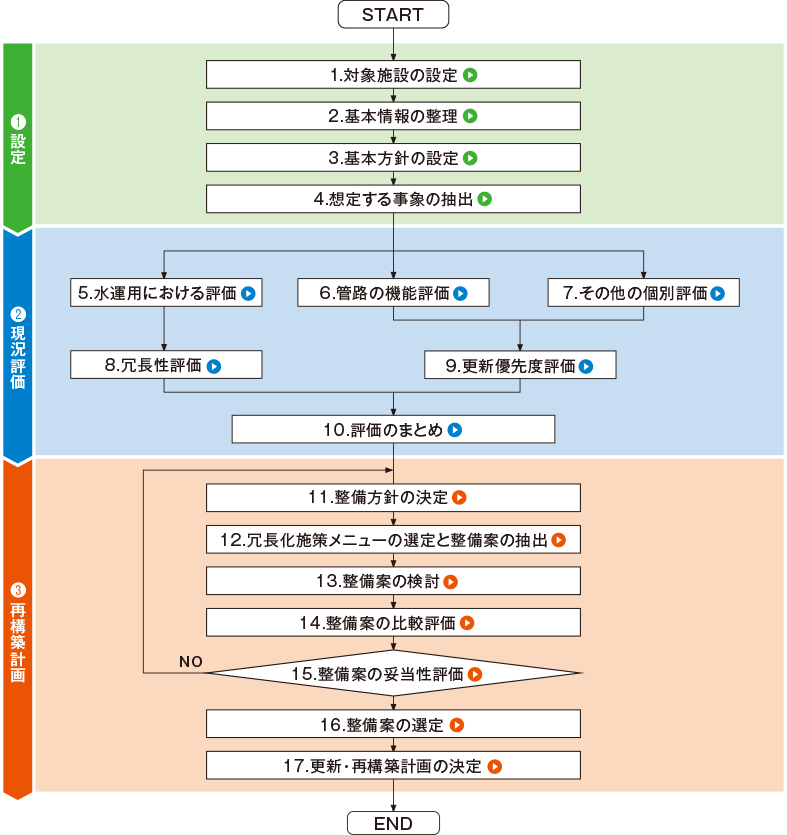





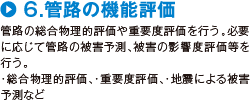





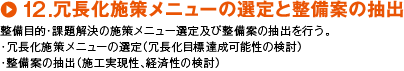
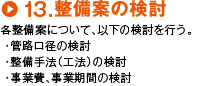
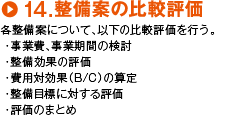



計画期間を10年から15年に設定し、設計に用いる計画給水量は計画期間ごとに設定することとしました。整備対象の管路は、計画期間終了後に運用を開始することとし、計画給水量は、運用開始後の最大給水量とします。例えば、水需要が減少する場合は、運用開始当初の給水量を用います。
人口や一人一日給水量が減少しない場合や、人口の偏在が発生する場合等、水需要が予測どおりに推移しない場合を想定して、計画した管口径でどの範囲の水量に対応できるかを把握し、計画期間ごとに見直しを行いながら進める手順としています。
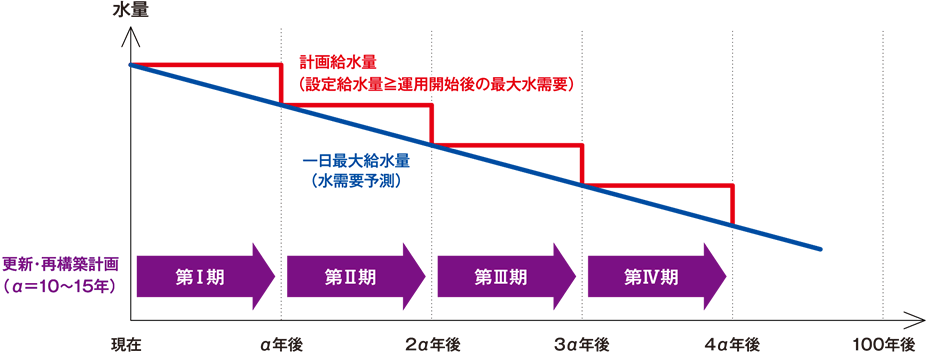
冗長性の確保に当たっては、給水量減少下での既存施設の能力を有効に活用する手法を組み込みました。
冗長性を有する基幹管路の便益については、評価方法が定められていないため、新たに定性的な評価項目の抽出を行いました。
さらに、次期更新時及び属具の更新時の費用低減、もらい事故時の被害低減、等について定量化する方法を提案しました。