
我が国の水道事業では、給水人口や給水量の減少を前提に、老朽化施設の更新に対応するために様々な施策を講じなければならないという、未だ経験したことのない時代が到来しています。
人口減少やそれに対応するための広域連携等、将来の不確実性に対応するために、基幹管路等の重要管路の再構築と、効率的な管路網への再整備に伴う管網管理に関する課題及びその解決策を明らかにすることが求められています。そのため、公益財団法人水道技術研究センターでは、平成26年度から平成28年度までの3ヶ年にわたり、産官学連携による共同研究プロジェクトとして「将来の不確実性に対応した水道管路システムの再構築に関する研究(Rainbowsプロジェクト)」を実施しました。
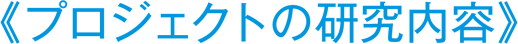

 計画手法の研究
計画手法の研究重要管路※の中でも、工事中の水運用や施工の難易度、事業費などの理由により、特に更新が難しい、大口径・単線の基幹管路に焦点をあて、計画手法を研究しました。給水量の減少を踏まえた口径設定の手法と、更新に合わせて冗長化を図る新たな計画手法を検討し、事業体の計画事例を交えながら手順としてまとめました。
 再構築における課題と対策の研究
再構築における課題と対策の研究事業体の重要管路※に関する取り組み事例を、計画、設計、施工、維持管理の面から調査し、課題に対する取り組みとその解決策についてまとめました。重要管路の更新・再構築に取り組む機運を高めるため、先行事例をまとめた事例集を作成しました。※本研究では、基幹管路と重要施設給水管路を重要管路と位置づけています。
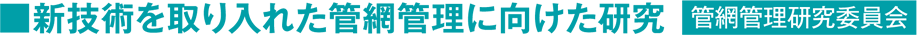
 適正口径選定手法に関する研究
適正口径選定手法に関する研究将来の不確実性を主に人口減少に起因する水需要の減少と捉え、新たな管網管理手法として、将来の水需要減少に伴う配水圧の不均一や滞留水による水質低下などの問題を解決すべく、平常時、火災時及び事故時における水理面、水質面を満足できる配水管網全体の管路口径を決定する適正口径選定手法を提案しました。また、消火用水量が適正口径選定に与える影響を検討しました。
 水道のスマート化に関する研究
水道のスマート化に関する研究水需要減少に対する管網管理手法として、管網管理のスマート化の可能性について検討しました。限られたリソースでの管網管理への適用性について、ICTの活用に着目し、ICT類の事例集の作成やICT導入による管網管理へのメリットについて検討しました。
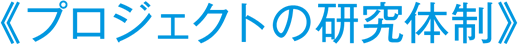

| 重要管路研究委員会 | 管網管理研究委員会 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 首都大学東京 小泉特任教授 | 鳥取大学 細井副学長・理事 |
| 学識者 | 東京都市大学 長岡教授 首都大学東京 荒井准教授 |
大阪大学 鎌田教授 名古屋大学 平山准教授 鳥取大学 増田准教授 |
| 事業体 | 大阪広域水道企業団、神奈川県内広域水道企業団、川崎市上下水道局、埼玉県企業局、千葉県水道局、東京都水道局、新潟市水道局、八戸圏域水道企業団、広島市水道局 | 神奈川県企業庁企業局、神戸市水道局、さいたま市水道局、札幌市水道局、豊中市上下水道局、名古屋市上下水道局、福岡市水道局、横須賀市上下水道局、横浜市水道局 |
| 企業 | ㈱クボタ、㈱クボタケミックス、㈱栗本鐵工所、コスモ工機㈱、JFEエンジニアリング㈱、積水化学工業㈱、大成機工㈱、㈱東京設計事務所、㈱日水コン、日鉄住金パイプライン&エンジニアリング㈱、日本水工設計㈱、日本鋳鉄管㈱、㈱日立製作所、日之出水道機器㈱ | ㈱NJS、㈱クボタ、㈱栗本鐵工所、㈱ジオプラン、水ing㈱、積水化学工業㈱、㈱東芝、㈱日立製作所、日之出水道機器㈱、フジテコム㈱ |
| (公財)水道技術研究センター | (公財)水道技術研究センター |